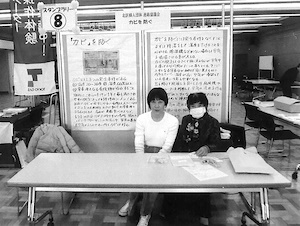| 婦人時報は年間購読料1800円(送料込み)です。購読希望の方メールで申込できます。 |
| ■2025年1月1日付 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■謹賀新年 | ||
|
ことしは再生可能エネルギーがさらに花開きますように 〜陸上風力に加え浮体式洋上の増設やソーラーにも次世代型が登場 | ||
| ▲back | ||
| ■再生可能エネルギーを最大に 〜国のエネルギー基本計画案 | ||
|
2040年度の新しいエネルギー基本計画(案)では、発電量に占める再生可能エネルギー比率を最大化して4割?5割、火力については3割?4割、原子力利用度を2割程度にしたいとしています。 直近の2023年度再生可能エネルギー(再エネ)の発電量は太陽光、風力、水力などを含めて全体の22・9%でした。 計画ではこれに新たに薄くて曲げられる、軽い次世代太陽電池の「ぺロブスカイト型」の実用化を急ぎ、風力では海上に風車を浮かべて発電する「浮体式洋上風力」発電などをさらに拡大し、40年度の電源構成で再エネを4〜5割程度まで増やす見込みです。 一方火力の発電量は2023年度統計で68・6%。大半は二酸化炭素を多く排出し、国際的にも批判される石炭火力でした。 私たちの依存度が高い火力については、40年度には3〜4割へと減らす計画ですが、限りなく石炭火力を「0」へと舵を切ったイギリスと比べ、国は石炭にアンモニアを混ぜて燃やす手法でCO2量を抑える、あるいは排出したCO2を地中に貯留する(CCSの事業化)などの対策を講じ、今後も利用を継続していく方向です。 原発は最大限活用に一転 また原子力発電については、2023年度の発電に占めた割合は8・5%に留まりました。にも拘らず40年度には発電量の2〜3割になるように、最大限活用へと一転しています。 東京電力福島第一原発事故の深刻さを受け、従来の基本計画では「可能な限り原発依存度を低減する」とされていました。しかしながら、岸田前首相は「GX(グリーントランスフォーメーション)脱炭素電源法」などを定めて、原発回帰へとそれまでの方針を転換し、原発の60年超運転を承認しました。 石破内閣の新計画案では、災害大国日本を忘れたか、古い原発施設の建て替えに加えさらに新たな原発建設を容認しています。国は本案に検討を加え、今年度内に決定する模様です。 東京地婦連ではかねてより再エネの拡大を願い研修し、原発に依存しないよう発言してきました。暮らしの安全に関わる「原発への依存度2?3割案」には賛成できません。 | ||
| ▲back | ||
| ■ガソリンの環境対策 地球に優しい合成燃料と廃食用油のSAFに期待 |
||
|
化石燃料のガソリン等を脱炭素化し、環境対策を進めるため、石油元売り会社とガソリンスタンドなど石油由来燃料を販売する業界は、近年「合成燃料」と「SAF」の開発と実用化に向けた取り組みを加速させています。 まず合成燃料ですが、原料に再生可能エネルギー由来の「CO2フリー水素」と「CO2」を使用して製造する、脱炭素(カーボンニュートラル)時代に適応した液体燃料と言われます。工程を経てこれを石油のように精製すると、ガソリンやジェット燃料、軽油などの様々な化石燃料に代わる合成燃料に変身するもので、大手のENEOS(エネオス)は2030年代に商用化する意気込みだそうです。 合成燃料は普通のエンジン車はもとより、エンジン・モーターで走るハイブリッド車にも活用が可能といわれます。 既存のガソリン供給施設を将来有効利用出来ると言われ、全国的なインフラを新たに整備しなくてよいというメリットもあります。「CO2をリサイクルしても排出量を減らすだけ」という声もありますが、マイカーなどガソリン車の買い替え、供給施設の新設などの膨大な環境負荷を思えば、消費者には合成燃料供給への期待感があります。 もう一方のSAFは、持続可能なリサイクル航空燃料のことです。 コスモ石油他2社は、堺市とSAFなどの原料となる使用済み食用油資源化促進を図るため、「持続可能な社会の構築に向けた廃食用油の資源化促進に係る連携および協力に関する協定書」を締結しました。 大阪府内のイオンモールに回収箱を常設し回収する形で、SAFを製造し供給する仕組みは出来ており、徐々に稼働する運びだそうです。航空燃料には環境負荷低減の必要性が叫ばれており、消費者参加の素晴らしい取り組みが始まりました。 | ||
| ▲back | ||
| ■初のPFAS全国調査 水道水の水質基準を早急に | ||
|
深刻な有機フッ素化合物PFASによる汚染問題が各地で発生している中で、ようやく環境省は昨年夏に全国の自治体や水道事業者に、「令和2年以降の水道水の水質検査実施の有無、PFASが検出された場合は最大濃度、検査をしていない場合はその理由・実施予定など」の報告を求め、PFASの検出状況や検査実績の把握を行いました。上水道のほか簡易水道などを含む約1万2000事業者を対象とする初めての全国調査に乗り出したわけです。それ以前はPFASの水質検査は自治体などの任意実施とされていたため、環境省は全国の汚染状況を掌握していなかったものです。調査は国土交通省と協力し行われました。 11月29日に結果が公表され、全国の公営上水道・簡易水道などを管理する3755事業者からデータ収集したところ、2024年度に調査した地点では、有害物質が検出された事業者は333ありましたが、2020年度に政府が決めた水道水の「暫定目標値」水1リットル当たり50ナノグラムを下回っていました。(PFASを代表する2物質の合計値) しかし今回対象事業者の約4割が、「PFASの検査は義務付けられていない」「費用負担が重い」などの理由で測定していません。「水道水のPFASに水質基準がない」現状では、発ガン物質汚染源の放置問題が発生します。水質基準は喫緊の課題です。 | ||
| ▲back | ||
| ■葛飾区 第61回秋野菜品評会 受賞者全員が若い後継者 | ||
区民賞の審査員には、区民の皆さんが公募での参加です。倍率は3倍で男性3人、女性6人が当選しました。 コマツナ、ダイコン、キャベツやみかん等36品目で279点の出品の中から、特別賞(農林水産大臣賞、東京都知事賞、葛飾区長賞)等の14賞、優秀賞、最優秀賞以外では、私たちが区民審査員として「食べてみたい、料理してみたい、作ってみたい」などの視点でコマツナ、みず菜、ダイコン、サツマイモ、キャベツ、ブロッコリーの6点を区民賞として選びました。 今年の天候は「9月から12月の4カ月間、平年より2・5度も高い異常な高温」だと、たびたびニュースや天気予報で知らされていましたが、天候本位の野菜作りは本当にご苦労があったと思います。 私は区民審査委員として表彰式に参加しましたが、受賞者が全員若者で、立派な後継者が育っていることに感動しました。葛飾区は23区の中でも、都市農業が存続している貴重な区です。 野菜は私たちの健康にとって不可欠な食べ物です。安全・安心な新鮮野菜を若い後継者たちにいつまでも作り続けて頂きたいと思います。 | ||
| ▲back | ||
| ■北区消費者生活展 千草婦人会は「カビを防ぐ」をテーマにパネル展示 | ||
私たち北区婦人団体連絡協話会(千草婦人会)は、「カビを防ぐ」をテーマに、どうしたらカビを防げるか等、パネル2枚にまとめ展示しました。身近な問題なので来場者と色々お話が出来ました。 フェアでは、北区リサイクラー活動機構「プラスチックリサイクルのゆくえ」、東京ほくと医療生活協同組合健康づくり委員会「すこしおについて」、男女共同参画推進ネットワーク「女性の視点から防災を考える」、王子警察署「特殊詐欺等の被害防止について」、東京ガス株式会社「ガスでもっと安心・安全・豊かな暮らし」、北区防災ボランティア「マイタイムライン」、第二ワーク・イン・あすか「地域の方々との交流」、東京都生活文化スポーツ局、軽量検定所「くらしを守る軽量制度」、リサイクル清掃課「ごみ減量について、フードドライブ実施」等、生活に役立つ情報がいっぱいのパネル展示や手作り物品の販売などがありました。 ステージでは、SDGs(エシカル)X防災・体験講座と貯金箱づくりで楽しくお金を学ぼう!、の消費者力レベルアップ講座が開かれ参加者は熱心に聞いていました。 来場者には、エコバッグ、絆創膏のプレゼントがあり、各ブースでもボールペン、ウェットティシュ、ハンカチ等、色々な物を頂き、袋いっぱいにされて大喜びでした。山田北区長も、全ブースを熱心に回られ激励してくださいました。 参加された方々にとって、各ブースの展示が、家庭生活に活用されたら幸いです。 実行委員会の皆様、そして北区産業振興課消費者生活センターの皆様には、大変お世話になり、御礼申し上げます。 | ||
| ▲back |